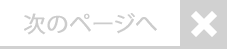インターフェースについて その4
・サンプリング周波数とビット深度
他によく見る数字では、この2つが挙げられます。
サンプリング周波数は録れる波長の細かさ、実用面では「どれくらいの高低差の幅のある音を扱えるか」の指標です。
CDは44.1kHzで、人間の可聴域の限界とされる20kHzに近い22.05kHzまでをカバーしています。
48kHz、96kHz、192kHzなど高性能なものもありますが、データ量が増大してPCに負荷がかかる割りに、効果はプラシーボ程度です。
なので、48kHzや96kHzが上限でも十分事足りると思います。
インターフェースが対応していても、実際そこまでの音を出せるスピーカーを用意するほうが難しく、効果の判別も厳しいです。
ビット深度は音の縦の繊細さで、ダイナミックレンジ、ボリューム面に影響するものです。
CDは16bitとなってますが、24bitと聴き分けできる人はたまにいます。
質の良いヘッドホンや大型スピーカーでは音の強弱差がわかることがあります。
これももちろん数字が大きくなるほどPCへの負荷が大きくなるので、16bitか24bitで制作するのが落としどころとなるでしょう。
音質を決める部分ではありますが、CDの音質である44.1kHz、16bit以上の性能があれば実用上の差はないでしょう。
制作時はもっと別の部分で悩むことになります。
・DSPについて
DSPはDigital Signal Processorの略で、複雑なデジタル信号処理機能の総称です。
インターフェースにおける具体的なものとしては、付属のリバーブやコンプレッサー機能にあたります。
リバーブやコンプレッサーは、収録時に必要になりますが、リアルタイム処理はプロセッサに対する負荷が大きいため、インターフェース側が単独で行えると便利です。
昔の環境では、アウトボードという形でこれらのエフェクトを専用の外部機器でやるのが普通でしたが、技術開発が進んだため、インターフェースにも基本的なものが搭載されるようになってきています。
楽曲制作をするにあたってあるとないとでは大きく違うので、活用をしっかり視野に入れて選びましょう。
(管理人へのご連絡は不要です)