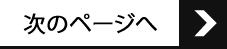インターフェースについて その1
複数のモニターで曲をチェックする、マイクを使って音を取り込む。
外部の電子楽器の音とPCのソフト音源の音を混ぜて制作する。
DTMを本格的にやろうとすると、音の入出力を一手にまとめてくれるものが必要になります。
オーディオインターフェースはその役割を果たしてくれる、裏方な機材です。
・選ぶ際には使用シーンを考えること
PCに繋げるにはポートの形状や対応OSを見ていけばいいのですが、どれくらいの規模で使うことになるのかを想定すると、品を選ぶ明確な基準になります。
友人らとバンド活動して同時に録りたいのであれば、ボーカル、ギター、ベースなどその分だけマイク入力ができるミキサー型や大型が適しています。
一方、宅録と呼ばれる一人制作が主であれば、マイク入力は弾き語り用やステレオ入力用に2つあれば事足り、シンセサイザーなどからのライン入力ができるものや、モニター出力の多いものが好ましいです。
ノートPCと共に持ち運びたいのであれば、バスパワーの小型のものが候補に挙がるでしょう。
基本的に音の入出力がメインの働きなので、単純にポート数が多くなるほど高くなります。
数が明らかに多いものはスタジオ用途です。
音質が気になる方は、店頭で自分の耳で確かめる以外に確かな方法はありません。
筆者の個人的なことを言わせて頂くと、インターフェースの音質が制作に及ぼす影響は1%にも満たないと考えていますので、そこまで気負わずに選んでも大丈夫だと思います。
・バスパワーとセルフパワー
PCについてで若干触れましたが、インターフェースは母艦からの電源供給で動くバスパワー式と、独自で電流を引くセルフパワー式の2つに分かれます。
それぞれの長所と短所を抑えておきましょう。
・バスパワー式
メリット
コンセント不要、ほぼ小型で持ち運び便利
デメリット
ハブの使用、他接続機器の影響で動作不良になる可能性
単独で動作しない、ポート数は限られる
・セルフパワー式
メリット
単独で動作するものもある、ポート数に余裕がある、母艦側の影響が少なく安定性が見込める
デメリット
ほぼコンセント必須、使用場所が限定される、携帯性があまりない
長所短所は割とはっきりしているので、迷うことは少ないかと思います。
また、正式に対応を発表している製品でも不具合が起こることがあります。
ドライバ対応状況を製品名とOS名で検索し、チェックしておきましょう。
(管理人へのご連絡は不要です)