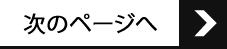ミックスの目的、エフェクトの分類
作曲、編曲は感覚的なものもあれど、ほとんど基礎的な音楽理論に則っています。
しかし、昨今クオリティが高いと思われる曲を作るには、ミックス、エフェクトの力が欠かせません。
生演奏主体のものであっても、きれいに仕上げるには適度なミックスが必要になります。
・ミックスの目的
ミックスの目的は大きく2つに分けられます。
楽器ごと、メロディーごとに調整する音作りのものと、全体のバランスを鑑みて調整するものです。
先にやるのは前者で、まず音源についている調整項目を弄る音作りから始まります。
新しい音源は楽器に対して相性の良いエフェクトがついていることが多く、これを操作するだけでもかなり勉強になります。
作曲、編曲していくうちにこの音をもっと目立たせたい、あるいは遠目に地味にしたい、展開に合わせて変化させたいという欲求が出ると思います。
適切なエフェクトを選んで差し挟み、目的通りに調整していきましょう。
曲の続きを書くうちに元の調整を変更する必要も出てくるので、実際には臨機応変に行うことになります。
曲全体ができあがってきたら、後者のミックスに移ります。
イヤホン、ヘッドホン、スピーカー、できるだけ多くのモニターを使いながら、楽器ごとの個性が出るよう、全体が良いバランスになるよう調整します。
出しすぎている(大抵作曲者の好み)音域を抑えてクリップしにくくしたり、いらない帯域をカットして音圧を上げやすくしたり、位置関係を調整したりといったことを行います。
やれることが多く、最初のうちはできたつもりでも扱いきれてないことがほとんどですが、作曲数を重ねて聴き比べると上達加減がわかるので、根気よく研究を重ねることが大事です。
・エフェクトの分類
加工の方法、工学的な分け方ではなく、作曲者目線の使い方で分類してみます。
実際にはもっと凝ったエフェクトや、別リストの目的に使うことのあるエフェクトもありますが、大まかなまとめとして捉えてください。
代表的で入手しやすい、使うジャンルの広いこれらを中心に解説していきます。
エフェクトは曲を豊かにするのに便利ですが、曲の表現によっては使わないという選択肢もあることを忘れないでください。
(管理人へのご連絡は不要です)