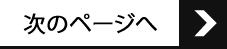フィルター
空間、細部調整の目的も大きいのですが、こちらで解説します。
実際の機能はワウワウ、イコライザと同系統の周波数関連のものです。
・効果について
電気回路上の「濾波器」であり、特定の周波数帯を絞る目的で使われます。
カットする箇所により、以下のように名前分けされています。
○ローパスフィルター(LPF)
低い部分だけを通す、つまり高い音をカットしていくタイプ。
○ハイパスフィルター(HPF)
高い部分だけを通し、低い音をカットしていくタイプ。
○バンドパスフィルター(BPF)
中くらいの音だけを通す、高低両面をカットするタイプ。
○バンドエリミネーションフィルター、ノッチフィルター(BEF、Notch)
中くらいの音だけをカットするタイプ。
その中でもカットする範囲が特に狭いものをノッチフィルターと呼ぶ。
LF、HFと書かれているパラメータは、直接的に低域、高域を指していたりしますのでご注意ください。
フィルターは録音編集、オーディオ編集ソフトでよく使われますが、DTMではメインとしてあまり使われません。
イコライザのほうが柔軟性に優れる傾向にあるためです。
他の呼び方をされているフィルターは、「周波数帯に着目して調整するシミュレーター」といったものが多いようです。
・基本的なパラメータ
○Q
絞る帯域の先鋭度、または選択度。
この値が小さいほど広く緩やかな範囲で絞り、大きいほど狭く急な範囲で絞る。
他は、利きを名前のノブ1つで済ませているものが大半です。
・活用シーン
細かい削り調整などはイコライザのほうがやりやすいので、フィルターの削り具合、特性を活かした音作りがメインになってきます。
ローパスを強くかけるとこもって鼻の詰まったような音に、ハイパスを強くかけると軽く薄い音になります。
バンドパスはリッチさを抑え、遠く感じる音にすることができます。
性格を変える、という点ならバンドパスエリミネーションやノッチを使います。
質感、距離感ともに変わるので、繊細な音源ほど合わないケースが増えていきます。
自身がざっくりしたエフェクトなので、大味な音源のほうが相性が良いと言えます。
曲全体にかける時は、展開に合わせて利きやオンオフを調整する流動的なものと、かけっぱなしにする固定的なものの2種類に分けられます。
後者は調整が困難なので、なるべくスピーカーを使って聴き比べましょう。
(管理人へのご連絡は不要です)