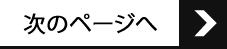リバーブ その2
・活用シーン
テクノの入ったロックやエレクトロなど電子楽器多めのジャンルでは、アルゴリズム系がよく採用されます。
響きの良さを重視する場合はアルゴリズム系の出番と言えます。
IR系はほとんどの場合、自然さの再現に使われます。
ライブハウスでのロックやジャズ、コンサートホールでのオーケストラなど実際の演奏をふまえて使うと効果が高まります。
複数の音源を組み合わせて使いたい場合は、音源側のリバーブを切り、外部からあてるリバーブを一つに決めて近い設定を使い回すと、全体がまとまりやすくなります。
同じものを使うか違うものを使うかは、ミックスに大きく関わるので意識しておきましょう。
曲全体にかける手ももちろんありますが、効果を逆算しておく必要があります。
ミックスの際にはリバーブを細かく分けて使いたいシーンが多いと思うので、手段を一本化に絞らないほうが応用が利くと思います。
エフェクトをかける順番としては、大抵最後になります。
アルゴリズム系→IR系の重ねがけはそれなりに見られますが、逆のパターンは少々難易度が高いです。
新しいソフト音源では、プリセットの時点で深いリバーブがかけられていることがよくあります。
第一印象がリッチになるという理由が大きいと思いますが、特にアコースティックな楽器の音は一旦リバーブを切り、他のリバーブを当てたりして元の音の良さを試すのをオススメします。
また、凝った設定のできる質の高いリバーブはそれなりに処理が重いです。
最終で挟むことが多いエフェクトなので、PCのスペックが厳しい場合は使わない時にオフにしておく、仕上げに入るまでは軽いもので代用するなど対策を考えておきましょう。
慣れない頃はこのエフェクトに頼りきりになり、ついつい強くかけがちです。
ヘッドホン、スピーカーなど、一つのモニターに偏らず、かけすぎてないかよく確認しましょう。
どんな曲でも使う基礎かつ重要なエフェクトなので、使う音源に合った残響を普段から追求する姿勢が大事です。
(管理人へのご連絡は不要です)