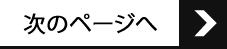リミッター
音量、つまりダイナミクス系エフェクトの代表格です。
音作り、最後のミックスなど様々な場面で使われます。
・効果について
「コンプレッサーと一緒」と混同している説明がよくあるのですが、実態と目的は違います。
リミッターは一定以上の音量を削ってしまう機能です。
実物では、音響機器で扱える限度を超えてしまう楽器の音量に対し、回路を保護し音を歪ませないために使われます。
DTMでの作曲でも、元のボリュームを弄らずに書いていっても、音を重ねていくうちにクリップします。
リアルさや強奏時の荒さを尊重してなるべくそのままに収録している音源などでも0dBを超えることはよくあります。
そうなるとミキサーでトラックごと下方修正するのが一般的ですが、そのトラックの小さい音まで崩したくない場合もあります。
そこで、大音量の頭だけを抑え、抑えた差分で全体の音量を底上げするという方向で使えるのがこのエフェクトです。
飛び出した音を潰すという性質上利き方が派手で、製品によって潰し方が異なります。
・基本的なパラメータ
○Threshold
音を削る音量ラインを決めます。
調整しながら、イメージが崩れない程度の歪みに抑えましょう。
○Output
削られた後の音量調整。
クリップしない範囲に留めましょう。
・活用シーン
基本的には、ミックス時に他との兼ね合いを考えながら、調整として個別に差し挟むものになります。
潰れ方はものにもよりますが、リアルさを売りにするオーケストラ楽器やアコースティックな楽器では相性が悪く、やりすぎは禁物です。
複雑な倍音成分によって音は構成されているので、飽和感を作りたいならエキサイター追加やサチュレーター兼ねての底上げのほうが適しています。
薄くかけない限りピークが雑になるので、パッドや管楽器などの繊細な音色に使うより、エレキギターやノイズを混ぜたシンセサイザーの音などに使いたいところです。
これらの音はリミッターで歪んでもあまり気にならず、場合によっては個性になるので音作りの一環として使えます。
曲全体にこの効果を期待する場合は、メタル、サイケ、ゴアと呼ばれるような過激さが求められる方向性のジャンルに限られてきます。
心地良い「耳への痛さ」を作り出すのに使われますが、作曲編曲、音域の住み分けがしっかりできた上での話なので、やや上級者向けの手法と言えます。
(管理人へのご連絡は不要です)