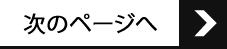ノイズリダクション
ノイズ除去という意味合いでは、こちらの効果のほうが一般的なイメージに近いと思います。
しかし、ノイズゲートとは最終的な目的は同じでも異なった使い方をします。
・効果について
雑音のパターンを音源から学習したり、ライブラリから引用したりして、ピンポイントで取り除く機能を指します。
収録中は雑音が常に鳴っていることが多いので、大抵このエフェクトもかけっぱなしになります。
雑音の除去は長年研究されていますが、他のエフェクトのように共通した原理があるわけでもなく、DAWのプラグイン、音声編集ソフトの両方で様々なタイプが出ています。
ギターのエフェクターにも存在しており、言葉の意味はかなり広範なので、どういったタイプのノイズ目的、除去方法なのか見極める必要があります。
・基本的なパラメータ
○Threshold
どんなタイプでも、この閾値を基準に調整します。
○Frequency
全ての周波数を曲線表示して、除去対象を設定できるイコライザ式のものも多い。
○Learn
ONにして音源をある程度流すと、雑音のラインを推定して自動設定してくれるものがある。
・活用シーン
接続する機材が多くなると目立つ「サー」というヒスノイズ、空調や電源周りが発生源の「ブーン」というハムノイズ。
こういった不可避で常に入るノイズを除去するのに活躍します。
一定の音量レベルに達さないものを監視して除去するノイズゲートと、周波数帯で調整するイコライザ、マルチバンドコンプレッサーを組み合わせたようなものが多いです。
実際、上記のノイズは周波数帯が大体決まっているので、一度除去できるポイントを見つけられると同系統のノイズも除去できます。
気をつけなければいけないのは、ノイズのみを100%除去するものではないという点です。
収録された時点で原音とノイズは混ざっているため、ノイズを完全に聴こえないようにすると、原音もその分損なわれます。
収録時にクリップ、音割れしてしまった音声などがその典型で、元の音自体が歪んでいるため、ノイズリダクションでいくら頑張っても綺麗にはなりきりません。
あくまでノイズを目立たなくさせるに留まる機能だということを理解して、音割れしないように収録し、整えるためにこのエフェクトを使いましょう。
(管理人へのご連絡は不要です)