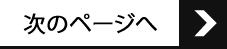イコライザ
視覚的に見やすいエフェクトです。
音楽プレイヤーにもよくついていますが、調整には慣れが必要です。
・効果について
EQと略されることが多いです。
扱う周波数帯を決め、そこの音量を上げたり下げたりします。
○○バンド・イコライザというものは操作できる周波数帯の数を表していて、グラフィック・イコライザは帯域を順に並べてわかりやすくしたものです。
ダイナミック・イコライザは音量変化に対応して効果がかかります。
DAWの基本機能としてついていますが、個別のものは上下のさせ方に独自のアルゴリズムを使ったり、リミッター設定など凝った調整ができたりします。
エンハンサー、エキサイターは広範な音程に対応して強化するのに対し、イコライザは特定の周波数帯だけを調整します。
「楽器本来の音のバランスを崩さない」という点では不利であることに注意が必要です。
その特性から、音を強めるよりかは出すぎている部分を引っ込める用途のほうが向いています。
音を上げる場合はリミッター、コンプレッサー機能が含まれているものを使いましょう。
・基本的なパラメータ
○Frequency
調整する周波数帯を決めます。
○Q
絞る帯域の先鋭度、または選択度。
フィルターのものと同じ機能です。
○Gain
音量のコントロール。
・活用シーン
最もよく使われるのは、ベースやバスドラムの20~40Hzあたりの低域カットかと思います。
ほとんど聞こえないと認識されているためと思われますが、人間はその実振動も余韻として感じているため、やりすぎると軽くなります。
「音圧を上げやすくするためにカットする」というのも多いですが、これはその帯域が鳴っている楽器を無意識に多く使っているのが原因です。
全ての楽器の音がなるマスタートラックと個別トラックで比較し、曲に合った適切なバランスを見つけましょう。
また、ヴァイオリン、ピッコロ、エレキギターなどの出すぎた高音を抑えるのにも使われます。
これらの高音は少ないボリュームでも耳につくので、イコライザの常時制限が役に立ちます。
音楽プレイヤーに、ジャンルごとにイコライザ調整できるものがよくあります。
これはそのジャンルで強調されがちな帯域に偏らせるものなので、参考にはできますが、曲全体にかけるエフェクトとしての導入はかなり大雑把なものとなります。
音楽的なバランスが崩れやすいので、慎重に扱いましょう。
(管理人へのご連絡は不要です)