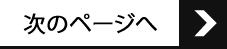曲の構成力について
スケール、コード、和声非和声、楽音と噪音などを解説致しましたが、他にも気になるところはあります。
曲全体の構成力についてです。
・曲は文章や物語のようなもの
最初の4小節、8小節で止まってしまって次が作れない。
嘘みたいな話ですが、割と聞くことがあります。
感覚や抽象に頼った説明が多く、幻想的なイメージを持たれがちな作曲ですが、実物は計算と地道な積み重ねの上に成り立っています。
文章を書く際、主旨を考え、説明から入り、具体的な中身を経て、結末を迎え、要点をまとめる。
物語を書きながら、起承転結を作って話を綺麗に成り立たせる。
実際はこれらの工程と変わりないんです。
設定だけ、クライマックスだけを考えても、それを作品という完成形にするのは難しいです。
メモのようにできた一部を保存するのは悪くありませんが、自分の中の主役を引き立たせるための、地味な脇役も作らなければなりません。
詰まりをなくすには、曲のイメージやスタンスを自分の中で確実なものにし、直感的に作れない部分を他の曲から学び、苦手意識をなくすことが鍵となります。
好きな音だけではなく、あまり意識の向かない音をあえて聴き、どう作用しているか分析する姿勢を持ちましょう。
曲の中にある物語性は、時間を経て連続的に作られていることを忘れないでください。
・構成上のテクニック
いくつか、曲に物語性を与えるためのテクニックを挙げてみます。
○同じコード進行、もしくは派生進行の繰り返し
4の倍数の法則を元に、コピーして同じものを繰り返したり、1つだけ変えたりします。
尺が欲しいができた雰囲気を大きく変えたくない、という時に使えます。
同じものの繰り返しでは、楽器6つのうち2つだけ記譜を変えるなどすると、落ち着きながら飽きさせない印象を持たせることができます。
○一部要素を無視
曲はメロディー、ハーモニー、リズムで成り立っていると説明していますが、曲中でどれかを抜いても構いません。
特にメロディーを意識から抜いて曲を作ると、イントロが作りやすくなると思います。
リズムを抜くと映画のオープニングのようなアンビエント系を作れますし、ハーモニーを抜くとエスニック系のエキゾチックな曲調を作りやすいです。
○高い音はサビで
一番盛り上がる部分以外では、高音の出を抑えましょう。
高音は心理的な緊張感をもたらすので、乱発より狙い撃ちが効果的です。
(管理人へのご連絡は不要です)