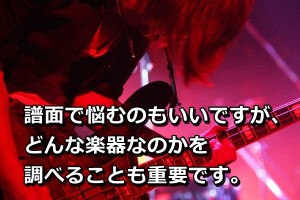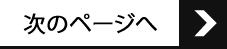耳コピってどうなの? その1
音楽経験のない方がDTMを始めようとして調べると、「耳コピ」という単語を目にすることがあると思います。
これは単純に、曲を聴覚だけを頼りにコピー再現することを指します。
作曲するにあたって、「とりあえず耳コピから始めろ」と促しているところも多いです。
しかし、これをやってオリジナリティは大丈夫なのか、どれくらいやればいいのか、わかりにくいものであることも事実です。
そこで、耳コピについての要点をまとめてみます。
・耳コピによって期待できる効果
まず、メリットを挙げておきます。
・楽器の音や編曲テクニックが区別しやすくなる
曲自体を解析する際に不可欠な能力である、「楽器1つの音を意識的に拾って聴く」ことができるようになります。
通常、意識に強く入ってくるのはメロディー、歌声といった部分ですが、それは他の楽器の音の構成が主役を目立たせるよう、裏方に徹しているからです。
その裏方の部分にあえて意識を傾けることにより、編曲の構成、テクニック、各音の関係性への理解を深めることができます。
慣れないうちは楽器の名前と音がなかなか一致しないかもしれませんが、数をこなすと「この音はあの音源を使えば大体再現できるな」という感覚が身に付きます。
自由自在に曲を作りたいならこの体得は必須なので、地道に覚えていきましょう。
・オリジナリティの元になる「引き出し」の確保
コピーに力を入れたからといって、オリジナリティが失われることはありません。
実際オリジナリティというのは曖昧なもので、出そうと思って出せるものでもありません。
また、これの元になるのが、好きな曲から得た小技、「引き出し」だと筆者は考えます。
曲全体のことではなく、強く惹かれる部分で、耳コピをする時にも自然とここに焦点を当てると思います。
人の感性によってそれは様々です。
独特のメロディーラインであったり、曲全体の雰囲気、音作りの調和であったり、エレクトロな音遊びであったりします。
それを真似ようと試行錯誤し、自分の中で合点のいく調整法を発見した時、それは今後いつでも使える「引き出し」に変化します。
曲を豪華に仕立て上げる編曲の鍵はここにあると言っても過言ではありません。
また、「目標ではなかったけど使えそうな音」も見つけることになると思います。
引き出しを確保し、そこから応用することがオリジナリティに繋がります。
(管理人へのご連絡は不要です)