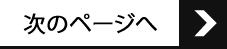ハーモニーに一工夫 その2
・スケールの理解と半音ズレの強烈な濁り
筆者は「ひたすら用語を暗記するより、実際に音を鳴らし、曲作りと音の感覚を自分なりに掴むことのほうが重要」と考えています。
なので、文字情報は最小限に留め、とりあえずやってみるという方向性で解説しています。
ここまでの説明でもどの音を使えばいいのかわからない、コード進行が作りづらいという方は、スケールを参考にしてみてください。
一定の雰囲気を保てる音の並びで、この中から1つか2つ飛ばしで音を選んで和音を作ると、使いやすいものになるはずです。
○メジャースケール
○ナチュラル・マイナースケール
スケールの詳細については「作曲、メロディーから編」で解説していますので、参照してください。
また、半音(黒鍵含めた全部の鍵盤の間隔)ほど隣の音(例:F4とF#4、B2とC3など)は同時に鳴らすと、どうしようもなく濁った不快な響きになります(トリルのような独特の奏法を除く)
基本的に、2~5半音くらいの間隔で音をとるのを守ると使える和音になるので、覚えておきましょう。
・強弱感やリズムを作り出す
進行を作れても、打ち込んだそのままではのっぺりした印象が拭えません。
ピアノやギターなどの減衰型の音だと音量が勝手に変化するので、ベロシティと発音タイミングだけ調整すれば大体使えます。
ストリングス、ブラスセクション、コーラスなどの自由型は強弱をつけないと面白くありません。
伴奏では白玉(全音符や2分音符など、長めの音符が表記上の特徴からそう呼ばれる)といった音価(音の長さ)のあるものがよく使われます。
また、細かく区切ってアルペジオ(分散和音、和音の構成音をタイミングをずらして上下一方向に一音ずつ演奏する)にしたものも多いです。
小節単体ではなく、曲全体や他の楽器との兼ね合いを考えるとこれらの修飾はやりやすくなります。
これも頻繁に変化させず、ある程度規則性を持たせ、4小節目だけなど一部にアクセントを作るとメリハリがつきます。
慣れるまでは大変だと思いますが、一つ一つ直しながらでいいので感覚を掴んでみてください。
これまで説明した4の倍数や繰り返し、転回形やコードの種類の見分け方、オクターブ違いで音の数を合わせるやり方などを駆使すれば、かなりの数のハーモニーを作ることができます。
(管理人へのご連絡は不要です)