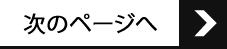編曲、曲構成について
・編曲面
テーマに恋愛が選ばれやすく、その性質上明るさ、華やかさ、爽やかさなどが重視されます。
これらの表現にはシンセサイザーのバッキングの中で、メロディアスな歌詞を歌わせるのが適しています。
シンセの音は横に広い(周波数、倍音的に多くの成分を含ませやすい)ので、コードをそのまま弾いて示すものは数を控えめに、エフェクトを重視して調整すると聴きやすいスッキリしたものになります。
アクセントとして使うシンセとは区別して音の数を考えましょう。
ギターを導入する際は、曲の方向性で音源を選びましょう。
音を少し足したいだけの場合は、単独ではチープ気味なものでも合わせると良くなることが多いです。
ギターソロやアドリブのようなフレーズ、バンド感を意識したいなら記譜に応えられるリアルなものを導入したいところです。
音源を買うのもいいですが、弾けるなら録ってしまったほうが高いクオリティを得られる場合もあります。
高域の弦楽器において、単独の音はオブリガートを軸に、ストリングスなどの合奏は2、3程度の和音で使うとそれらしくなります。
ポップスで合わせる場合はリアルさ重視や楽器独自の響きを再現しているものより、適度にシンセ臭さの残るシンプルなものが使いやすいでしょう。
主役になることは少なく、適応力のあるものが重宝されるため、付属音源やフリーで配布されているものでも十分賄えます。
生々しさを消したい場合は、コーラスでぼやかしたり、イコライザで端の音を抑えて丸めたりしましょう。
ドラムについて、バスドラムは元の音は大きく録られていてポップスには合いにくいので、大抵イコライザやハイパスフィルターなどで低い部分を削ることになります。
スネアや金物もリリースやリバーブを少なめにして、しつこくならないようにすると軽やかな曲になります。
・曲構成
典型的なパターンとしては、イントロ→Aメロ→Bメロ→サビ前→サビが挙げられます。
サビから入るようなものもありますが、その後に曲の全体の説明としてイントロ、メロと入っていきます。
Aメロなどから作ってしまった場合は、コード進行の安定した根元となる音、キーを探し、合ったメジャーかマイナーのコードで4か8小節ほど先に挟んでみましょう。
それが一番簡単なイントロの作り方ですが、それを繰り返し聴いてイメージを固めた後、作り変えていくこともできます。
(管理人へのご連絡は不要です)